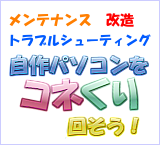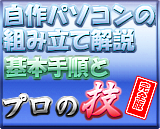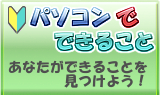知っておきたい!パソコンの基礎知識 |
USBメモリとは | パソコンの基礎知識 |
USBメモリとは
USBメモリはデータ記録するための記録媒体です。
一般的にUSBメモリで通じます。
しかし、略して「USB」は大間違いです。
USBとはユニバーサルシリアルバスの略で、正しくは接続規格のひとつです。
つまり、USB端子に接続する製品、例えばプリンターやSDなどのメディアリーダーなどを、USB接続する接続タイプのことを指し、USB接続の○○というのが本来の正しい使い方です。
そのため、USBメモリを指し「USBが壊れた」「USBを失くした」という言い方は意味不明となります。
例えばコンセントプラグ一体型の小さな照明がありますが、その照明を指し「コンセント壊れた」「コンセント失くした」では同じく意味不明ですよね。
「USBに保存した」なら通じるのは通じるのですけどね。
しかしながらUSBと言えばUSBメモリと勘違いする人が多く、特に多いのがプリンターの接続方法を確認する時に「USBケーブルですか?」(他にLANや無線LANでつないでいる人もいるため)と聞いた時に、
「USB(メモリ)は使ってる」といった回答をする人がとても多く、スムーズに話が進みません。
一般的にそこそこPCについての知識があると、USBメモリをUSBと略すことはありません。
もしこれまでUSBと略していたのなら、これを機に略さずにUSBメモリと言うようにしましょう。
製品の多くは平たく棒状の「スティックタイプ」なため、一時期は「メモリースティック」と混同する方も多かったのですが、メモリースティックはソニーの製品の登録商標で、USBメモリとは全く別の商品です。
USBメモリは以前に主流であったフロッピーディスクのように扱えるため、急速に普及しました。
もともとデバイス(周辺機器など)の接続はパソコンの電源を入れる前から行わなければいけなかったのですが、
USBという接続規格は端子に対して「接続された」「外された」などの動作を監視するため、Windows起動後であっても、USBメモリの抜き差しが可能になっています。
USBメモリが接続されると、コンピューター内に「リムーバブルディスク」などとして表示されます。
リムーバブルディスクを開いた場所に、エクセルやワードで作ったデータを保存したり、コピーしたりすれば、そのデータを持ち運べるわけです。
また、ドキュメントなどのフォルダをコピー、貼り付けすればそれだけでドキュメントのバックアップが取れます。
まだファイルがどこに保存されているか理解しようをご覧になっていない場合は、そちらもご覧下さい。
USBメモリの取り扱い上の注意点
メモリはパソコンで使われるメモリモジュールに限らず、USBメモリに使われる物も静電気に弱いため、取り扱いには若干注意が必要です。
(参考 : パソコンのメモリってどれくらいの静電気で壊れるの?)
しかし、一般使用される商品であるため、通常のメモリよりも静電気に対しての抵抗は高くなっているので、メモリモジュールのように「静電気を放電してから触る」というほど神経質に扱う必要はありません。
ただそれでもキャップをせずに持ち運ぶなどはしない方が良いでしょう。
USBメモリで良くあるトラブルは「読めなくなった」「データがおかしくなった」などです。
USB端子はUSBメモリ側も接続端子側もそれほど強くはありません。
そのため、過度に抜き差しを繰り返すといずれアクセスできなくなることもあります。
また、USBメモリなどに使われる不揮発性メモリ(通電していなくてもデータが保持できるメモリ)は、書き換え回数に制限があります。
そのため、大量のデータを頻繁に書き換えるなどの使い方は寿命を縮めやすく、最終的にデータへのアクセスができなくなります。
これは必要ではなくても大きめの容量の物を使うことで、同じ書き換え回数であっても寿命は長くなります。
詳しくは省きますが、書き換え回数とは製品そのものではなく、メモリブロックに対して行われるからです。
- 正しく覚えてる?パソコンの名称
- メモリってどういうもの?
- HDDってどういうもの?
- DVDドライブやBlu-rayドライブなどの光学ドライブ
- パソコンの起動と終了の意味
- アクセスランプを見るようになろう
- ファイルとは
- ファイルがどこに保存されているか理解しよう
- コピーと貼り付け
- バックアップとは
- ショートカットとは
- OSとは
- インストールとは
- ゴミ箱とは
- 周辺機器を使うために必要なドライバの意味を理解しよう
- パソコンは遅いものと認識しよう
- ソフトをたくさん入れると遅くなる理由
- USBメモリとは
- 画面のサイズと解像度
- インターネット接続の流れとプロバイダーとは
- プロバイダーからのメールは必ず確認しよう
プライバシーポリシー
Copyrights (C) 2006-2018 iwane-web All rights reserved.